サロン D’アキ・カウリスマキ
アキ風の隙間に添える、北欧式ワビ・サビの美学 時代の中心に立つ監督が必ずしもいい監督とはかぎらない。すくなくとも、僕のようにひねくれた人間には。その周辺にいる味のある監督たちをひとりごちながら、静かに発見するのが映画好き...
 映画・俳優
映画・俳優アキ風の隙間に添える、北欧式ワビ・サビの美学 時代の中心に立つ監督が必ずしもいい監督とはかぎらない。すくなくとも、僕のようにひねくれた人間には。その周辺にいる味のある監督たちをひとりごちながら、静かに発見するのが映画好き...
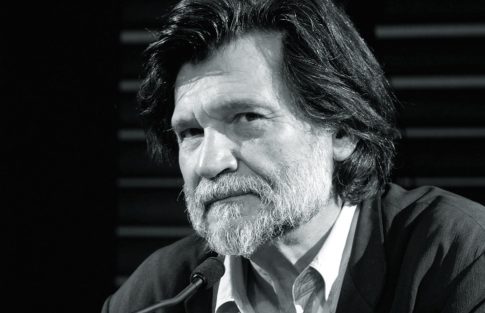 映画・俳優
映画・俳優あれは「シネ・ヴィヴァン・六本木」がまだあった80年代の終わりだったか。 ビクトル・エリセのデビュー作である『ミツバチのささやき』に はじめて出会ったときの感動は、40年近く過ぎた今も、全く色あせてはいない。 いまだに、大切で幸福な映画体験の代表として、ことあるごとに「語ってしまう。 一つの事件のように、それほど、大きなショック、感銘を受けた映画なのだ。
 映画・俳優
映画・俳優ここで取り上げる映画作家たちは、 これまでの路線を大いに逸脱する名前などでてはこない。 繰り返し繰り返し言及してきた作家たちを ときに、重複する言葉や言い換えによって ああでもない、こうでもないと上書きするだけのことだ。 相変わらず、しまりのない、だらだらとした独り言が続く。 すべての作品を見て、細部にまでこだわり シネフィルの真似事をしたいわけでもない。 そこには自分としてのフィルターがある。 はじめに「好き」ありき。
 映画・俳優
映画・俳優アニエス・ヴァルダの眼差しが好きだ。 彼女の語りが大好きなのである。 時に祖母のようでもあり、また、歳の離れた友達のようであり、 また、この世のあらゆる境界線上に生きる創造物のようであるアニエス。 そんな彼女が映画で使用する文法の自由さに驚き いつのまにか、その世界に引き込まれてきた。 そんなぼくが敬愛してやまないこのシネアストについてのサロンを ここに言葉で開いてみたい。 ただし、ここでは彼女の仕事を言葉でうまく語るよりも 同時に彼女が知らない人にも向けて、 そのアウトラインが親しみを共感できるガイドになればいいと思う。 極めて低い敷居になることを願う。
 映画・俳優
映画・俳優ここまで、勝手にわが偏愛女優小論を重ねてきたが トリを飾るのはこの人しかいない。 若尾文子については、ここでは彼女の主演作品のなかで、 何度も言及し、ひたすらその思いを綴ってきた。 とりわけ、増村保造という映画作家の元で放った 強烈な印象を中心に、思いを傾けてはきたが、 本来、彼女は、一つのジャンル、傾向に収まりきるような女優ではない。 それこそ、舞台から、テレビドラマ、CMなどをこなす、八面六臂の活躍は 昭和の乗りをこえて御年90の大台にも突入している。 溝口健二作品では、女優道を仕込まれ、 小津や川島雄三といった名匠のもとでキャリアを重ねながら 本領たる増村作品にで合う。 『青空娘』にはじまり『最高殊勲夫人』『卍』といったものから、 以後中心にかたる日本女性にはない、強さをもった役で 印象を決定づける作品はもとより、 さらには吉村公三郎や市川崑といった監督の元では 洒脱なコメディエンヌとしての才も十二分に発揮してきた、 文字通り日本映画の隆盛期を支えてきた大女優である。
 映画・俳優
映画・俳優ミューズであることの孤独と永遠 ぼくが愛してやまない映画作家、フェリーニの妻でありミューズであったジュリエッタ・マシーナが、そのフィルモグラフィのなかで彼女が出演している作品はさほど多くはない。おまけに、いつも、どこかバ...
 映画・俳優
映画・俳優最近、ストリーミングで梶芽衣子60周年コンサート『セッテ ロッソ』を観た。 彼女の映画を通じて、その数々の歌に親しみはしてきたが、 ここに立つ彼女は78歳。 そこには芸歴60周年のずしりとした重みもあり、 老いてなお、凛とした佇まいでステージに立つ彼女に 驚かされ、そしてしびれるのだ。 時に、姉のように、そして母のような面影を宿す彼女は、 やっぱり、唯一無二な存在だなと、つくづく思った。
 映画・俳優
映画・俳優イングマール・ベルイマンの映画を語るとき、 リブ・ウルマンという女優の存在の大きさを避けて通ることはできない。 それは彼女が代表作に数多く出演したからというよりも、 ベルイマン映画の本質そのものが、彼女を通して 初めて可視化される“触媒”に他ならなかったからである。 試しにテレンス・ヤングでチャールズ・ブロンソンと共演し その妻役を演じた『夜の訪問者』などのウルマンとでも見比べてみれば その違いは歴然としている。 彼女は、ハリウッド的女優でも、フランス映画のアイコニックな女優も似合わない。 まさにベルイマンにとって唯一無二なミューズだった。
 映画・俳優
映画・俳優基本的に、アメリカンな女優は苦手だ。 あえて紋切り型ないい方が許されるとして、 大柄で、オーバーアクション、その上、奥行きがない脳天気さで 演技をまとめあげてしまう力技を駆使するハリウッド的な女たち。 誰とはいわない。 だが、ジーナ・ローランズはちょっと違う。 いわゆるいい女でありながら、激しい感情に揺すぶられはするが それでも、彼女は常に苦悩する。 甘えない。動きを止めない。 たとえ、それが間違っていようといまいと、突き進む。 怖い形相でにらみ、そしてときに、そこから涙を滲ませ スクリーンに生身の魂を刻んできた女。
 映画・俳優
映画・俳優そんな裏話はさておき、日本映画史において、「大女優」という響きが これほど曖昧で、同時に切実に感じられる存在が他にあるだろうか? 子役でデビューし、天才と謳われ 日本映画の隆盛期を支えてきた高峰秀子は華やかなスター街道を歩みながら とくに、“強き女”として記憶される女優ではなかった。 名だたる監督たちの元で、着実に映画産業を支えてきた一面と、 仕事に対する厳しさ、プロフェショナルを生涯失わなかった女優として その名を残した軌跡は、文字通り大女優とよんで差し支えない。 そんな高峰秀子という女優について、 ここでは、成瀬己喜男作品における高峰秀子をめぐって、 改めて書いてみたい。