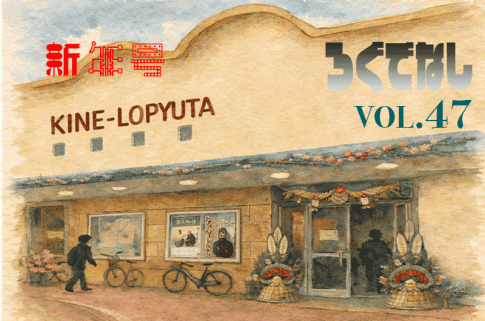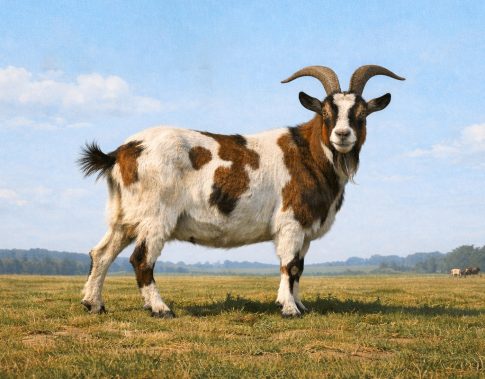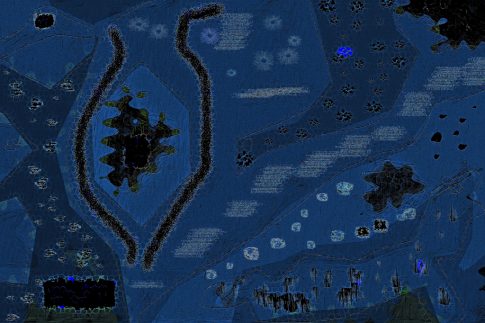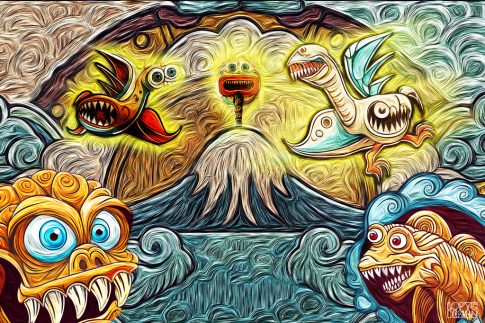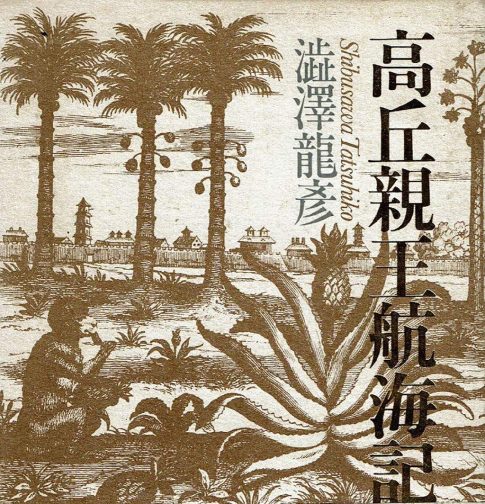森一生『不知火検校』をめぐって
1960年、同期のライバル雷蔵に差をつけられていた折、 勝新に巡ってきたひとつの転機があった。 犬塚稔が脚色したこの宇野信夫の同名戯曲『不知火検校』において 勝新は極めて異様で魅力的な主人公を演じたことだ。 監督は大映黄金期を支えたMR活動屋、森一生。 映画史において、盲目の主人公が人々の心を射抜くというのは、 決してありふれた現象ではない。 だが、そこに勝新太郎という異端の俳優が登場すると、 その図式はがらりと変わるのだ。 詐欺、強姦、強殺教唆、殺人、悪びれることなく悪行の限りを尽くし それでいて、なんともいいがたい色気を放っている。