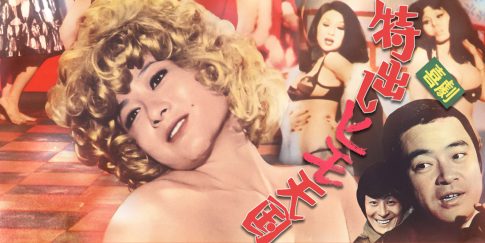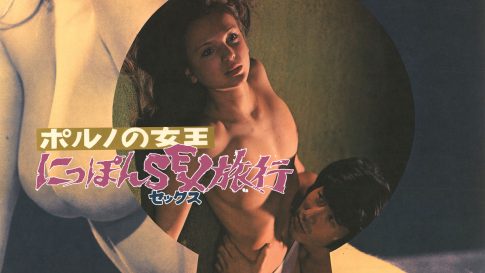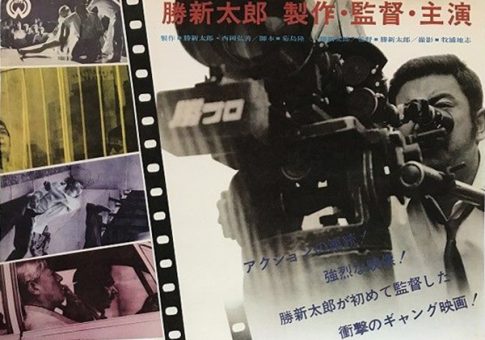大九明子『勝手にふるえてろ』をめぐって
この作品を見たのは、確か、今はなき飯田橋のギンレイだったと思うが なにと二本立てだったかまでは忘れてしまった。 さて、正月気分も抜け、このシリーズのラストを飾る、 大九明子による松岡茉優主演の『勝手にふるえてろ』は、 ラブコメというもっとも“回収されやすいジャンル”を選びながら、 その回収を最後まで拒否する、奇妙ながらも誠実な映画である。 恋愛映画の顔をしているが、実の所、恋愛についての映画ではない。 成長物語の形式を借りているが、成長をほとんど描いてなどいないのだ。