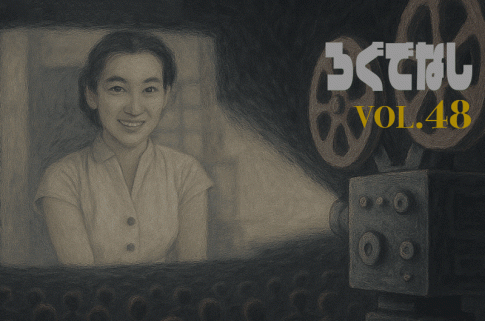ジーナ・ローランズ小論法
基本的に、アメリカンな女優は苦手だ。 あえて紋切り型ないい方が許されるとして、 大柄で、オーバーアクション、その上、奥行きがない脳天気さで 演技をまとめあげてしまう力技を駆使するハリウッド的な女たち。 誰とはいわない。 だが、ジーナ・ローランズはちょっと違う。 いわゆるいい女でありながら、激しい感情に揺すぶられはするが それでも、彼女は常に苦悩する。 甘えない。動きを止めない。 たとえ、それが間違っていようといまいと、突き進む。 怖い形相でにらみ、そしてときに、そこから涙を滲ませ スクリーンに生身の魂を刻んできた女。