B級美学の豪華絢爛エンターテイメントを彫る
その昔、まだ銭湯という公共の場に通っていた頃の話をしよう。
隣で身体を洗っている大人の背中一面に
なにやら絵のようなものがはっきり見える。
そうだ、刺青だ、とは当時の無垢な頭じゃわからない。
そのスジの裸体を見て、子供ながらに胸がザワめいた。
人の肌に、絵があるのはなんで?
しかも、なんだか迫力のあるその妖しさに
流石にどこか危険な匂いを嗅ぎ分けたとみえ、ドキドキはした。
しかし、それをジロジロと眺め続けることや、
真実を確かめることなど、できるはずもなかった・・・
時代は変わって、街ゆく若者たちは
それをファッションの一部として取り込み、
海外のスポーツ選手らはこれ見よがしに、タトゥを誇らしげに晒し、
この物憂げで、後ろめたい想いを一掃した。
しかし、ここ日本ではいまだにある一定の縛りがあり、
この封建的社会はそれを断じて許さない。
所詮、タトゥといってみても、
それが一つのカルチャーだという考えは、
いつの時代も自由な若者たちだけの勝手なルールなのかもしれない。
「刺青お断り」の看板の理由を程なく理解し始めるころ、
なるほど、これはあまり触れてはいけないもの、
それが、外れた道の美意識だという常識を備えることに他ならず、
それゆえに、惹きつけられてしまう何かが常にあった。
そうした思いの「刺青」という符牒を
今度は文化的側面として、初めて認識することで
社会の別の側面がみえてこようとは思わなかった。
さて、本題は、その刺青をテーマにした作品から、
大正生まれの鈴木清順が撮った映画『刺青一代』に進もう。
わけのわからない映画の中では
比較的わかりやすい部類に入ると思う。
ある意味、(清順にしては)まともすぎる映画といえるかもしれない。
男気溢れる高橋英樹のかっこよさ、
それを慕うヒロイン和泉雅子の可憐さ。
そして何と言っても、凝りに凝った構図主義、映像主義。
視覚の美学が炸裂するラスト15分は見ものである。
確かに、こんなヘンテコな演出をしなければ
単なる人情篤き任侠ものに過ぎない。
弟をかばった兄の思いがどこか野暮ったくはあるが、
それがドラマとしてはキモなのだから。
その意味では、この映画はおそらく
同性愛的傾向のある人間には
一種、たまらない映画として映るかもしれない。
つまり、女が情的に入り込む余地のない映画として、
まさに、男と男の美学が終始貫かれているからだ。
これぞ清順美学の決定版だ。
それは、男子たるものなんぞや、
という日本男児の心意気でもあるのだ。
とはいえ、映画としてみると、
スター高橋英樹に比べ、弟分の仏具師健次を演じた
新人花ノ本壽ではいささか物足りない。
その風貌は、どことなく、若きころのあの水谷豊を彷彿とはさせるが
演技の技量は足元にも及ばない。
そのあたりは、目を瞑るとしても、やはりあの怒涛の構図ラッシュ、
松尾嘉代が傘を渡してからのラストの盛り上がりこそが清順美学の真骨頂だ。
実に圧巻である。
これぞ活劇の真髄である。
画面が過度な演出を伴ってどんどんヒートアップしてゆくなか、
赤の氾濫を始め、雷鳴、雨、照明効果に彩られながら
動的な横スクロール長回しで勢いを加速し、
青や黄色、色とりどりの襖が開いてゆくマジック演出に
もはや十八番の真下からのど迫力殺陣シーン。
こうなればもう誰にも止められない、やりたい放題である。
しかし、これら全てが鈴木清順である証であり、
他の任侠映画との決定的違いなのだ。
レコード盤が真っ二つになったり
真っ赤な靴の男を始め、とにかく赤、赤、赤の赤ラッシュで、
挙句に朱肉のクローズアップといったベタな演出のおまけ付き、
血と血の抗争を最大限に盛り上げておいて、
はらりはだけた着物の下に雨に打たれる白狐が覗く。
最後はそんな高橋英樹に華を持たせて
クールに任侠ドラマを〆て終わるのだ。
砂浜に、パラパラと花札を散らせながら、
女をおいて、警官とともに遠のいてゆく。
所詮、暴力がテーマでもなければ愛がテーマというわけでもない。
何か道徳観念を植え付けるでもない。
ひたすら、観念を美学で押し通すこの映画のダイナミズムに
映画の神が降りる演出に痺れるのだ。
これぞホーリーシネマ、
国宝級映画彫物師の演出に、今酔わずしていつ酔うというのか。
B級美学の豪華絢爛エンターテイメントにおいて
この人の右に出る人など、もはやおりますまい。
肩で風切るような単純な男には、
あらてめてブルーの色彩に帯させる小憎い映画である。
The Rolling Stones – Waiting On A Friend
刺青一代を見終わって、真っ先にストーンズの『Tattoo You』のジャケットを思い出していた。このアルバムにはタイトル曲がないから一曲を贈るとすれば、
やはり「Waiting on a Friend」にしようと思う。
この曲には、激しい闘いの熱がない。
野心も、若さも、衝動も、すでに通り過ぎている。
ミック・ジャガーの声もとくに前に出ず、
ジャズ界の巨人、ソニー・ロリンズによるサックスの音色が
まるで言葉にならなかった感情の残響のように、ゆっくりと空気を満たしている。
『刺青一代』における兄弟愛が、感情のドラマではなかったように、
そのあたりのクールネスを満たすものでなくちゃいけない。
それは、誓いであり、構造であり、引き返せなくなった人生そのものだとしても、「Waiting on a Friend」が歌う〈友〉とは、再会を約束された存在ではなく、
むしろ、もう二度と肩を並べて歩けないかもしれない誰かを、
それでも心のなかで待ち続けてしまう感覚とでもいうのか。
そういうものが静かに流れている。
それはストーンズのメンバー間の絆であり、
大切な友との強いつながりを感じさせ、
運命共同体として生きてしまった者にだけ許される感覚だ。











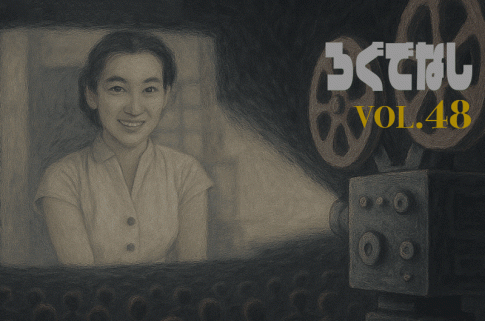

コメントを残す