聖なる病に魅入られて
この世のどこかに、自分と瓜二つの人間がいるかもしれない。
しかも運命共同体としてのツインソウル。
それをロマンと呼ぶか、神秘と呼ぶか、奇跡と呼ぶか、
それとも単なる妄想ととるかは、ひとそれぞれではあるが、
知らず知らずにそんな物語に引き込まれている自分がいる。
きっとどこかに、魂の分身が存在するにちがいないのだと、
そう考えることは別に罪ではないが、相応なまでに痛みと覚悟がいる。
むろん、理屈や確信などどこにもない。
ただそう思うから思うだけのことである。
クシシュトフ・キェシロフスキによる『ふたりのベロニカ』には
ポーランドとフランス、この二拠点それぞれに生きる若い女性がいる。
ふたりは面と向かい合うことはないが、見えない糸で繋がっている。
しかも、同じ時刻に生まれ、名前も見た目も瓜二つ。
そんな透明な糸が、互いに知らぬ者同士を天上から操るかのように、
運命の鼓動を、どこかで虫の知らせのように鳴らしはじめる。
そんな偶然を、声ではなく、光でもなく、
まずは音楽によって雄弁に語り始める、異様なまでに繊細な物語にせまってみよう。
映画を観終わって、感動を覚えたものなら
ポーランドのベロニカとフランスのヴェロニクという
“二人のベロニカ”が辿る人生の重なりに、
誰しも、説明のきかない胸騒ぎを覚えただろう。
いうなれば、これがドッペルゲンガー「自己像幻視」と呼ばれる幻覚。
だが、彼女たちを結びつける力は“運命”と呼ぶには少し強すぎるが
偶然で片づけるにはあまりにも繊細すぎる物語なのだ。
キェシロフスキはここで、ユング的なシンクロニシティを散りばめつつも、
意味のある偶然として、映画という詩の形式に落とし込み結晶化させた。
ソプラノ歌手と音楽教師を結ぶこの不可思議な糸、
それは、まるで世界のどこかで距離を越えて互いの弦を震わせてしまうような、
重力のない不可視の共鳴である。
ベロニカが生きる歓びの頂点で歌い、その響きが死を呼び寄せるとき、
遠いフランスで、ヴェロニクの胸は理由もなく締めつけられる。
それは錯覚でも、因果でもない。
“そこにいるはずのない誰か”の影が突然、
自分の胸の奥にそっと触れてくる、まさに同期そのものが動き出す瞬間だ。
その感覚こそ、この映画が描こうとした「聖なる病」としての合図ではなかろうか?
そういえば、晩年キェシロフスキ自身が心臓に病を抱えており
それが54歳という若さでの死因にもなったのはつとに知られている。
だが、ここでヴェロニカを襲ったのは肉体を蝕む方の病ではなく
いうなれば、幻覚であり、霊的なざわめきとして、
心臓麻痺というショッキングな一撃の共鳴を感じ取ってしまったのだ。
そのざわめきは、その人の中にだけ降り立った現象である。
ベロニカの声は、この世界のものとも思えないほど崇高に響きわたる。
あまりにも純度が高すぎて、まるで歌うという行為そのものが、
生命の中心にある心臓の鼓動を、外側へと垂れ流してしまうほどであり、
彼女がステージ上に立ち、まさに黄金の光に包まれて歌う瞬間、
観客は彼女の美しい歌声に感動すると同時に、
どこか“死の匂い”さえも嗅ぎとってしまうことになる。
なぜなら、彼女の声は生の極点として、その終点である死へと
接続してしまう危うさを孕むがゆえの美しさだったのだ。
音楽はここで、感情の背景としてではなく、運命の“警鐘”として鳴り響く。
彼女が高らかに声を放つほど、その音は
彼女自身の生命と引き換えに悪戯を企てる。
光は美しく輝けば輝くほど、死の影を濃く落とす。
この背中合わせの危険な遊戯を描かんとして、
キェシロフスキはこの瞬間、音楽を、そして肉体を通して発せられる声を
自身の病にも重ね合わせながら、「宿命の発声器官」として扱ったに違いないのだ。
一方、ヴェロニクは歌わない。
けれど、音楽を聴いた瞬間、彼女は説明不能の悲しみに崩れ落ちる。
これは彼女の中に眠る“もうひとりの自分”が激しく振動した瞬間であり、
“記憶なき記憶”としか言いようのない感覚を呼び覚ましてしまうのだ。
このとき観客は気づきはじめるだろう。
二人は単に音楽でつながっているのではない。
音楽そのものが、彼女たちの魂の構造そのものを映し出しているのだと。
映画の後半で現れるアレクサンダーのマリオネット劇。
いみじくも、人形は替えが利くように、二体用意されている。
これは二人の人生を象徴的に縮小した“運命の模型”だ。
糸で動く人形たちは、自由を手にしたいと願いながらも、
見えない力に導かれてしまう。
その姿は、ヴェロニクにも、そしてすでに失われたベロニカにも重なる。
ただ、ここで重要なのは、キェシロフスキが決して
「運命に操られている」という決定論に踏み込まない点だ。
描かれるのは、世界の呼吸に触れてしまった者だけが抱える
永遠に解けることのない謎であり、
誰かの手に支配されるような、そんなやわな物語ではないのだ。
アレクサンダーはあえて縮図の操作者として、
ヴェロニクの内奥に潜む“不思議な感覚”を引き出す存在だが、
彼自身もまた巨大な世界の流れに巻き込まれたただの語り部にすぎない。
操られているようで、操っているようで、実際には誰も主体ではない。
その曖昧さ、不透明さが運命の実態であり
この作品に宿る“神秘の温度”を形づくっているものなのだ。
キェシロフスキ組のカメラマン、スワヴォミール・イジャックによる
フィルター越しのカメラが捉える黄金と緑の光は、
ふたりの人生を包む“透明な膜”として、物語を優しく、
そして残酷に覆いながら運命を見届ける。
黄金は祝福の色であると同時に“見えない力に触れる”危うさをも示す。
緑は生と死の境界に横たわる霊性を帯びることとなり、
こうして、ベロニカの世界は黄金に満ち、
ヴェロニクの世界は柔らかな緑に揺らぐ。
だがその色彩の揺らぎは、互いの境界がときおり溶け合いながら
一瞬、世界が二重に見える瞬間を生み出し、死の共有を迫ってくる。
光が“世界の縫い目”さえも鮮明に、
そして残酷に浮かび上がらせてしまうこの光の操作こそ、キェシロフスキが世界を“霊的な深度”で捉えていた証拠であり、
彼が晩年に向かうほど現実の表層よりも、
その奥に宿る宿命の気配を撮りたがった理由だったのだろう。
べロニカの突然の死を、ヴェロニクは“喪失”としてではなく、
理由なき痛みとして受け取る。
これこそが本作に宿る“聖なる病”の核心だ。
この聖なる病、それは、世界の奥に潜む秩序やつながりに
触れてしまった者だけが抱える、祝福と呪いの入り混じった症状である。
それは、単に幸福に生きる者には気づけない領域にあり、
敏感すぎる者なら、それを“予感”として受け取ってしまうことになる。
いわば運命の導きに、ここではスポットライトが当たる瞬間である。
ヴェロニクが泣く場面、胸を押さえる場面、
ただ風の匂いに怯えるように立ち尽くす場面。
バスの中に、写真のなかに、もうひとりの自分を見出してしまう場面。
そうした同期は、“もうひとつの魂が消えたときの余震”を
受け取ってしまう代償に、痛みをともなって自覚することになる。
これがもうひとりの自分の存在が無意識にうちに抱えている病なのだ。
この病は決して治らないし、解釈すらもできない。
もとより運命として備わった特権でありながらも、
聖なる痛みでもあるのだから。
だがその無意識こそ、キェシロフスキが世界を信じる
真実の語り口だったのだと思う。
こうして彼の映画が神や運命を大いに語らないのは
偶然の深みに宿る世界の詩情に、だれよりも通底しているからに他ならない。
ベロニカの死は、ヴェロニクに奇妙な“第二の誕生”をもたらす。
彼女は歌う道を捨て、愛を選び、身体の声を信じるようになる。
その選択は、ベロニカの人生の続きを生きることでもあり、
もうひとりの自分への献花のようでもある。
この映画のラストシーン、ヴェロニクが父の家の木の幹に触れるシーン。
架空の作曲家ヴァン・デン・ブッデマイヤーの曲が
じわじわと影を落とし始めるとき、
そこで世界は静かにたわみ、運命そのものを重なり合わせる。
そして彼女の指先は、改めて
もうひとつの人生の記憶”に触れることになるのだ。
そこに言葉など入る余地はない。
『ふたりのベロニカ』は、決して愛や死や運命を語らない。
これは “世界に触れてしまった魂が発症する、聖なる病を刻印し、
音楽はその鼓動となり、光は膜となり、マリオネットはその縮図となるだけだ。
二つの魂は互いの姿を知らないまま、同じ震えを分け合い、
ひとつの世界の中で“透明な共鳴”として響き続ける。
そこは、単に病の悪戯として語られるドッペルゲンガー譚ではないのだ。
そして観客は気づくだろう。
人生の偶然は、ただの偶然ではなく、
ふとした瞬間、世界がそっと触れてくるための“秘密の合図”なのだと。
ひょっとすると、世界のどこかに、
自分のこの魂の震えが共振するものがいるかもしれないと。
しかし、それを享受したものだけが受け止めなければならない宿命がある。
この映画はその合図を、最も美しい形で見せてくれるのだ。。
それこそが、キェシロフスキが描き出す奇跡の実態であり、
それに見事応えたイレーヌ・ジャコブの宝石のような美しさが忘れられない。
“Van Den Budenmayer – Concerto In E Minor (SBI 152) Version 1798″ Zbigniew Preisner
ファン・デン・ブーデンマイヤーとは、単に脚本クレジットのためだけに、ズビグニェフ・プライスナーと
クリストフ・キェシロフスキ監督が「二人ともオランダを愛していたから」というノリで名付けた18世紀オランダの架空の作曲家のことである。 ちなみに他のキェシロフスキ作品の『デカログ』や『トリコロール/青の愛』『トリコロール/赤の愛』にも使用されている。とりわけ『青の愛』で「ヨーロッパ統合のための協奏曲」として流されている。またプライスナーはデヴィッド・ギルモアのアルバムで、多くのトラックのオーケストラを作曲して関わっている音楽家である。
]





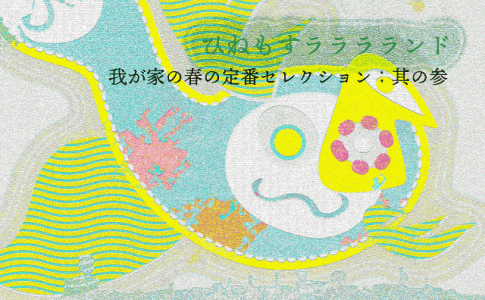







コメントを残す