衝動物を囲む世界
このコロナ騒動でひとつ気になっていることがある。
国民の、以前に増して他者への不寛容さが目立つということだ。
マスクや自粛、路上飲みなどをめぐって、それに抗う人間や
守れない人間に、身勝手だという論調だけが一方的に正義とされ
外れるものを十波一絡げにして袋だたきにするネトウヨたち。
そのうえ、何か起きたときは、自己責任で、
というふうにして冷たく烙印を押し
排除しようとする傾向がどうにも不気味でならない。
これは別に感情論ではない。
また綺麗事でもないし、単なる擁護といわけでもない。
率直に感じるところである。
正しい、間違いの線引きが曖昧な状況下で、
意見が片方に偏ってしまうことの危険性、
あたかも戦時中のごとき同調圧力を行使する様には、
こと全体主義傾向への警鐘を
もっと高らかに鳴らして然るべきではないか。
そんなことをふと考えてしまうのだが、
そういう声は残念ながらに聞こえては来ない。
こちらは無力な少数派なのである。
いったいなにがそうさせるのか?
人は失敗することに、そして同時に他者からの視線に敏感であり
社会から抹殺されることを極端に恐れている気がしてならない。
だから、頑なに自分の砦を守らねばならないとするのだろうか。
だれしも、わざわざ失敗などしたくもないし、
世の中を好んで混乱に陥れたいわけでもないはずだ。
ただ、若気の至りもあれば、衝動的にやってしまうような
愚かなことも、人間ゆえにないわけじゃない。
それゆえ、その代償は、自ら引き受けねばならぬわけだが
そこに待ち構える世間の厳しい視線にさらされることには、
人は耐えられないが故に、
無意識に予防線を張ってしまうのかもしれない。
西川美和による『すばらしき世界』は
佐木隆三による小説『身分帳』という原案からの映画化である。
そうした失敗者、元ヤクザの男が刑期を終え出所後
この社会でどういきてゆくのか、
周りの人間たちの反応とともに、
そうした世間の冷たい視線を浴びながら
生きてゆこうとする男のあがきその様子が描き出されている。
役所広司演ずる主人公三上は、その一本気な性格ゆえに
かっとなって火がつくと、自分で自分を抑えきれない。
なにしろ、積もり積もった「身分帳」の高さは1mmにも達するというから
この人物の素行が、いかに問題をはらんでいたかがうかがい知れる。
ちなみに身分帳とは、受刑者の生い立ちから性格、
刑務所内での態度、出来事など事細かく記載したまるまる個人台帳である。
元をだだせば、子供の頃、母親と生き別れになっており、
真の愛情を受けておらず、成長が止まっているともいえるし、
その分の負い目を、どこかで十字架として
背負って生きてきたのかもしれない。
そうして、その反動がいつしか反社会性力の一員として、
さらに人を殺めてしまった報いを含めて、
大部分の人生をムショ暮らしに甘んじてきた男である。
そんな身の上の男が、いきなり過去を清算して
今の社会にとけこめるはずもない。
もがけばもがくほど、その反動を受けざるを得ない環境から抜け出せず
これからの人生を、かろじて前を向いて模索していく姿に
リアルなドラマが滲み出す。
共感はただその姿にしかみいだせない。
が、問題は、〝前科者〟というレッテルだけではなく
社会そのものに適応できない性質が
自分自身でコントロールできない、という点なのである。
とはいえ、そんな三上に手をさしのべる人間もいる。
身元引き受け人の弁護士夫妻、福祉の人間、
小説家志望のテレビ局の若者、そして同郷のスーパー店長。
こうした人間模様は、一見するに
情と非情という二面ばかりに捉われがちな考えから距離をおいて
状況をみつめる手立てにはなる。
われわれが社会で生きてゆくセーフティーネットでもあるからだ。
それぞれに、立場立場を通して、この三上というフィルターを通じ、
世のあり様が身にしみてゆく。
ここが失われれば、個人は底辺から音を立て崩れ去ってゆくだろう。
とはいえ、その均衡のあやういマージナルに関わるだけに、
当然のことながら、さまざまに歪みを生むのもまた不可避なのだ。
まずは、仕事にありつけない。
仕事にありつけないということは生活がままならないということでもある。
つまり、ひとりで生きてはゆけぬ、ということだ。
かろうじて生活保護下にあっても、心は晴れない。
そうした境遇に甘んじていることに、苛立ちを覚えるばかりである。
世間からは前科者、殺人者としてのレッテルを貼られ
せいぜい寄ってくるのは、それをうまく利用しようとする、
野次馬的なマスメディアぐらいのものである。
三上は、確かに犯罪者である。
しかも同じ失敗を何度も繰り返してきた。
おまけに、かなり執拗なまでに残酷な殺人を犯した。
その思いは、反省どころか、しゃばの生活のストレスへと向けられる。
実際、目の前に起きている不条理に対し、
みずからの正義を発動させて、容赦無く暴力で解決しようする。
それは、結局、刑期を終えてなお変わらない当人の資質なのだ。
この男には、他人の目以上に自らのモラルこそが重要であり、
それでしか生きられないという不器用さにおいて
人生がつねに決定されてきた重みがのしかかる。
悪を繰り返してきたが、根は決して悪ではない。
だが、目の前にある悪を許せない、という矛盾を抱えながらも
少なくとも、そうした周りの理解はことのほか温かい。
けれども、自身がここから残り少ない人生を
今まで通りのやり方で切り開いてゆく時間は限りなく少ない。
本人は自分の倫理がそれを許さない。
欺瞞や綺麗事がどうにも許せないのだ。
暴力行為ははけ口でもあるが、堂々巡りはみていてもどかしい。
こうしたことにおいて、三上はやはり社会不適応者でしかない。
しかし、奥底には他人を慈しむ気持ちが備わっており、
無邪気に子供とサッカーをし、涙さえ流す。
あるいは、就職祝いに贈られた自転車に目を輝かせる。
そして周囲の期待と激励に応えようと、
なんとか必死に最後の一線だけは踏みとどまろうとする。
他者と共感し合えた時、あるいは認められたと感じる時
初めて、人間として自らの存在に目ざめるのだ。
しゃばはそうした実践の場でもある。
最初は小説のヒントにでもなるかというような安直な思いで
取材を兼ねて三上に近づくテレビディレクターの津乃田も
最後には三上の人間性にふれ、その動機をのりこえ心を開く。
もはや、カメラなどもつ必要もなく
不毛である関係から血がかよう瞬間を体験することになる。
しかし、ときはすでに遅しなのだ。
あらかじめ持病を抱える三上の唐突な死で
あっけなくすべては終わりをつげるが、
これは周囲の情に精一杯、人間として応えようとした男の幕切れとしては
無常なる代償というわけだ。
しかし、これがはたして「すばらしき世界」だといえるのか。
このタイトルがいかにも、アイロニカルにエンドロールに示される。
決して安直ではないヒューマニズムが、
あいまいなまま昇華されてゆく瞬間に、われわれもはたと目を覚ます。
この世は所詮、寛容でも不寛容でもなく、
ある一定の、いかんともしがたい倫理感によって流れているだけだと。
それを乗り越えるのは、なまやさしいものではないのだと。
社会のはみ出しものに対する愛情と残酷さが入り混じったこのドラマは
当人の死によって、唐突で決定的な結末が用意されているが
救いようも希望もない世界こそ回避されるが
ハッピーエンドとして、安易な結論に導かれるわけでもない。
おのおのが感じる「すばらしき世界」には
あまりにも漠然とした多様性だけがただよっている。
それは映画を離れた我々の現実にも横たわっている風景である。
今、見終わったあとの感情を、整理しながら書いてはきたが
これ以上うまく説明できない。
もう少し寝かして、じっくり味わってみるべき世界なのだろう。
ただ、今この現実の社会の縮図として掲げられるテーマが
興味深く刺ささってきたのは確かなのである。
ひとついえることは、当事者であれ、他人であれ、
目を背ける自由と、凝視すべきリアルが共存しているということだ。
それによって、この『すばらしき世界』が豊かな映画たり得ていることを知るだろう。
それにしても、役所広司という俳優の演技の幅は豊かである。
話題に上るたいていの日本映画で、ことごく顔をみてきた名優ではあるが、
個人的には、かならずしも好みの俳優というわけでもない。
むろん、演技をやその資質にケチをつけるつもりは毛頭ないし、
あくまでも、個人的な趣向からはズレがある、というだけのことである。
あまりに、役者的であり、ときにそれが完璧過ぎるがゆえ
こちらが圧倒され、ついてゆくのがしんどくなってくるほどである。
とはいえ、今、この日本映画界において、
最高の俳優のひとりであることは疑わないし
ある意味、この俳優への賞賛は惜しむべきものではない。
この『すばらしき世界』ではその個性が最大に発揮されており、
まぎれもなく成功し、この映画の根本をささえている。
それがいくつもの素晴らしいシーンにつながってゆく。
ひとつ感動的だったのは、部屋で一人死を間近にしたところに
同僚がくれたコスモスを握りしめ、虚空を泳いでいるあの目だ。
こんな演技をなかなか拝めるものではない。
映画冥利に尽きる瞬間でもある。
役に入り込んだ高揚感が、こんなにも静かで美しいものなのかと。
あるいは、全編妙に九州弁が達者だな、と思っていたら、
案の定、長崎出身であることに後で気づいた。
ここにも、役を完全に自分のものにしてしまう役所広司を後押しする、
面目躍如たる真の演技を引き出すための演出があるのだと気付いた。
西川美和は、そのあたり、じつに用意周到で確信的なのだ。
ともあれ、正直なところ、
犯罪者であるとか、殺人者であるということをさしひけば、
三上のような人間は少なからず、必要悪として、一定数いるのだと思う。
このコロナ禍の真の出口は、ワクチンを接種することでもなく、
無論、ゼロコロナに近づくことでもない。
感染が減った、収まったではないところで、事実をきちんと客観化した上で、
おのおの、他人に対する慈しみある視線とともに、
多少のことには寛容的であれと願う社会を取り戻すことにあるのではないか、
そんなことを教えられている映画だと感じ取れるかもしれない。
要するに、人間回帰である。
文字通り、それこそが「素晴らしき世界」なのではあるまいか。
Louis Armstrong – What a wonderful world
映画との映画との関連はタイトル名だけだが、
こちらはサッチモことルイ・アームストロング の『what a wonderful world』。
確か昔、ホンダ・シビックだったと思うが、CMに流れていたのを覚えている。
内容は現前の世界に対し肯定的に歌われる内容だが
元はベトナム戦争に向けた平和への祈りが込められている名曲である。






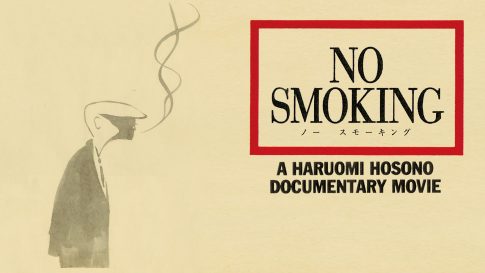






コメントを残す