ロピュマガジン【ろぐでなし】vol.48 酷薄的女優論
ぼくと、ここで取り上げる女優たちとの間には そんな酷薄的な距離がある。 高嶺の花として、それは手は届かぬが、いつも心内にあり、 スクリーンを通してのみ、存在するロマンティックな思いである。 妄想であり、盲信かもしれないし、単なる美化なのかもしれない。 でも、それでいいのだ。 それがいいのだ。 現実には夢はない。 それこそがスクリーンならではの夢であり、 ぼくが描く酷薄的女優論そのものなのである。
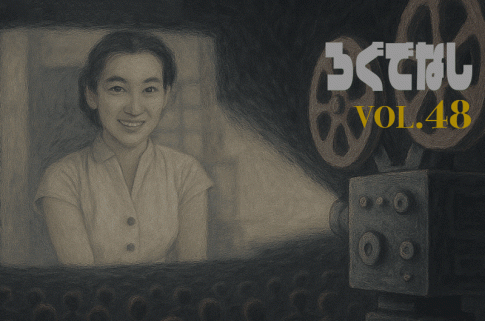 映画・俳優
映画・俳優ぼくと、ここで取り上げる女優たちとの間には そんな酷薄的な距離がある。 高嶺の花として、それは手は届かぬが、いつも心内にあり、 スクリーンを通してのみ、存在するロマンティックな思いである。 妄想であり、盲信かもしれないし、単なる美化なのかもしれない。 でも、それでいいのだ。 それがいいのだ。 現実には夢はない。 それこそがスクリーンならではの夢であり、 ぼくが描く酷薄的女優論そのものなのである。
 映画・俳優
映画・俳優そんな裏話はさておき、日本映画史において、「大女優」という響きが これほど曖昧で、同時に切実に感じられる存在が他にあるだろうか? 子役でデビューし、天才と謳われ 日本映画の隆盛期を支えてきた高峰秀子は華やかなスター街道を歩みながら とくに、“強き女”として記憶される女優ではなかった。 名だたる監督たちの元で、着実に映画産業を支えてきた一面と、 仕事に対する厳しさ、プロフェショナルを生涯失わなかった女優として その名を残した軌跡は、文字通り大女優とよんで差し支えない。 そんな高峰秀子という女優について、 ここでは、成瀬己喜男作品における高峰秀子をめぐって、 改めて書いてみたい。
 映画・俳優
映画・俳優一時期“ツンデレ”という言葉がもてはやされたが、 ぼくにとっての元祖ツンデレ女優はモニカ・ヴィッティ、その人である。 彼女を思い浮かべるとき、多くの観客はまず、 沈黙の中に立ち尽くす姿を想起するだろうか? 無機質な建築、荒涼とした風景、途切れがちな会話。 その中心で、彼女は何かを語ることも、激しく感情を噴出させることもなく、 ただ世界と噛み合わない感受性として佇んでいる。 それは、ミケランジェロ・アントニオーニ映画におけるヴィッティであり ふたりの巡り合いが生んだ、 20世紀後半の映画史に燦然と刻まれし、最も象徴的な「虚無の女性像」である。
 映画・俳優
映画・俳優伝説と呼ばれしものは、永遠に燃え上がるために、この世を早く去る。 そんな格言めいたことばを、ふと呟きたくなるひとりの女優がいる。 彼女の名前はフランソワーズ・ドルレアック。 いうまでもなく、妹は歳は一つ違い、 フランス映画界の大女優カトリーヌ・ドヌーブ、その姉として名が刻まれている。 世間広しといえ、ぼくにとって、美しい姉妹といえば 映画史のなかで、この二人以上に比較しうる存在がいない。 さらにいえば、ぼくは圧倒的なまでに姉ドルレアック派なのである。
 映画・俳優
映画・俳優アヌーク・エーメは実に恋多き女だった。 4度の結婚、離婚を繰り返している。 そのなかには、『男と女』で共演をきっかけに結ばれた サラヴァを立ち上げたSSWピエール・バルーも含まれる。 蜜月期、わずか3年の月日だが、遊吟詩人的なバルーとの恋もまた 詩的インスピレーションの賜物だったにちがいない。 ピエールはのちに「彼女は嫉妬深いところがあってね」、 そんなことをいっていて、一気に現実に引き戻された記憶があるが、 それでも、スクリーンを通して見る彼女が魅力的だったことに なんら変わりはなく、その女心に寄り添いたくなる男たちにとっては そのギャップこそが彼女へと恋を走らせてしまう要因なのかもしれないと思った。 多分に漏れず、ぼくもまた、そんな女優にときめいた。
 映画・俳優
映画・俳優永遠のアジアンビューティ、その身体性の品格について 最初にマギー・チャンを見初めたのは、ウォン・カーウァイの『欲望の翼』でのたった1分でいいから時計を見ろとレスリー・チャンに口説かれるシーン、あのドラマチックな一分間の恋...
 映画・俳優
映画・俳優この作品を見たのは、確か、今はなき飯田橋のギンレイだったと思うが なにと二本立てだったかまでは忘れてしまった。 さて、正月気分も抜け、このシリーズのラストを飾る、 大九明子による松岡茉優主演の『勝手にふるえてろ』は、 ラブコメというもっとも“回収されやすいジャンル”を選びながら、 その回収を最後まで拒否する、奇妙ながらも誠実な映画である。 恋愛映画の顔をしているが、実の所、恋愛についての映画ではない。 成長物語の形式を借りているが、成長をほとんど描いてなどいないのだ。
 映画・俳優
映画・俳優さすらいのジャンキーに憧れて 最近では全自動が主の雀卓で、手積みの感覚がわからないのだがそれでも、牌のジャラジャラという音が郷愁をくすぐってくる。ぼくがひょんなことから麻雀を始めたのは五十を超えてから、しかもまったくなん...
 映画・俳優
映画・俳優数あるロマンポルノのなかでも、 ひっそりと置き去りにされながらも、記憶に残る一本の映画がある。 小沼勝監督による『OL官能日記 あァ!私の中で』にふれてみよう。 華のある傑作というより、むしろ埋もれてしまう作品であるにもかかわらず、 そこには70年代という時代の“自由の匂い”が、 いまなお、微かに漂い続けている強烈な一本として忘れ難い映画だ。
 映画・俳優
映画・俳優古くは任侠道にはじまり、ときにはフィルム・ノワール、 シュールからゲテモノまで、玉石混交の闇市のような日本映画史。 そのなかから「さて、今日はどれにしようか」と考えるのが いわば映画狂のサガというものだ。 面白い掘り出し物を探すなら、東映。そして石井輝男。 概ね相場は、そこに落ち着く。 さらに「東映性愛路線」と聞けば、 まあ、だいたいの匂いは想像の域を出まい。 だが中身は、蓋を開けるまでわからない。 そこがびっくり箱的な面白さである。 そしてこの『異常性愛記録 ハレンチ』 これこそは、その想像をはるかに下回り、 同時に、底なしに突き抜けてくる一本である。

クリエーターlopyu66によるアウトプットウェブ
住所
123 Main Street
New York, NY 10001
営業時間
月〜金: 9:00 AM – 5:00 PM
土日: 11:00 AM – 3:00 PM
