ロピュマガジン【ろぐでなし】vol.48 酷薄的女優論
ぼくと、ここで取り上げる女優たちとの間には そんな酷薄的な距離がある。 高嶺の花として、それは手は届かぬが、いつも心内にあり、 スクリーンを通してのみ、存在するロマンティックな思いである。 妄想であり、盲信かもしれないし、単なる美化なのかもしれない。 でも、それでいいのだ。 それがいいのだ。 現実には夢はない。 それこそがスクリーンならではの夢であり、 ぼくが描く酷薄的女優論そのものなのである。
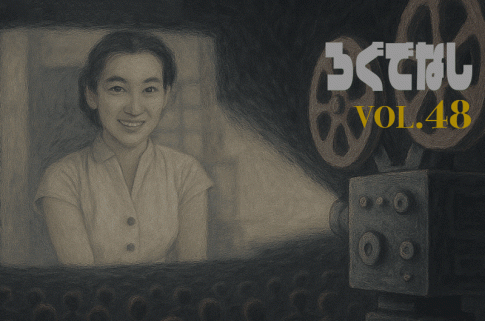 映画・俳優
映画・俳優ぼくと、ここで取り上げる女優たちとの間には そんな酷薄的な距離がある。 高嶺の花として、それは手は届かぬが、いつも心内にあり、 スクリーンを通してのみ、存在するロマンティックな思いである。 妄想であり、盲信かもしれないし、単なる美化なのかもしれない。 でも、それでいいのだ。 それがいいのだ。 現実には夢はない。 それこそがスクリーンならではの夢であり、 ぼくが描く酷薄的女優論そのものなのである。
 映画・俳優
映画・俳優ここまで、勝手にわが偏愛女優小論を重ねてきたが トリを飾るのはこの人しかいない。 若尾文子については、ここでは彼女の主演作品のなかで、 何度も言及し、ひたすらその思いを綴ってきた。 とりわけ、増村保造という映画作家の元で放った 強烈な印象を中心に、思いを傾けてはきたが、 本来、彼女は、一つのジャンル、傾向に収まりきるような女優ではない。 それこそ、舞台から、テレビドラマ、CMなどをこなす、八面六臂の活躍は 昭和の乗りをこえて御年90の大台にも突入している。 溝口健二作品では、女優道を仕込まれ、 小津や川島雄三といった名匠のもとでキャリアを重ねながら 本領たる増村作品にで合う。 『青空娘』にはじまり『最高殊勲夫人』『卍』といったものから、 以後中心にかたる日本女性にはない、強さをもった役で 印象を決定づける作品はもとより、 さらには吉村公三郎や市川崑といった監督の元では 洒脱なコメディエンヌとしての才も十二分に発揮してきた、 文字通り日本映画の隆盛期を支えてきた大女優である。
 映画・俳優
映画・俳優ミューズであることの孤独と永遠 ぼくが愛してやまない映画作家、フェリーニの妻でありミューズであったジュリエッタ・マシーナが、そのフィルモグラフィのなかで彼女が出演している作品はさほど多くはない。おまけに、いつも、どこかバ...
 映画・俳優
映画・俳優最近、ストリーミングで梶芽衣子60周年コンサート『セッテ ロッソ』を観た。 彼女の映画を通じて、その数々の歌に親しみはしてきたが、 ここに立つ彼女は78歳。 そこには芸歴60周年のずしりとした重みもあり、 老いてなお、凛とした佇まいでステージに立つ彼女に 驚かされ、そしてしびれるのだ。 時に、姉のように、そして母のような面影を宿す彼女は、 やっぱり、唯一無二な存在だなと、つくづく思った。
 映画・俳優
映画・俳優イングマール・ベルイマンの映画を語るとき、 リブ・ウルマンという女優の存在の大きさを避けて通ることはできない。 それは彼女が代表作に数多く出演したからというよりも、 ベルイマン映画の本質そのものが、彼女を通して 初めて可視化される“触媒”に他ならなかったからである。 試しにテレンス・ヤングでチャールズ・ブロンソンと共演し その妻役を演じた『夜の訪問者』などのウルマンとでも見比べてみれば その違いは歴然としている。 彼女は、ハリウッド的女優でも、フランス映画のアイコニックな女優も似合わない。 まさにベルイマンにとって唯一無二なミューズだった。
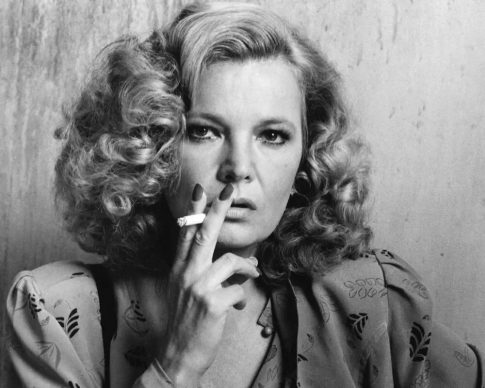 映画・俳優
映画・俳優基本的に、アメリカンな女優は苦手だ。 あえて紋切り型ないい方が許されるとして、 大柄で、オーバーアクション、その上、奥行きがない脳天気さで 演技をまとめあげてしまう力技を駆使するハリウッド的な女たち。 誰とはいわない。 だが、ジーナ・ローランズはちょっと違う。 いわゆるいい女でありながら、激しい感情に揺すぶられはするが それでも、彼女は常に苦悩する。 甘えない。動きを止めない。 たとえ、それが間違っていようといまいと、突き進む。 怖い形相でにらみ、そしてときに、そこから涙を滲ませ スクリーンに生身の魂を刻んできた女。
 映画・俳優
映画・俳優そんな裏話はさておき、日本映画史において、「大女優」という響きが これほど曖昧で、同時に切実に感じられる存在が他にあるだろうか? 子役でデビューし、天才と謳われ 日本映画の隆盛期を支えてきた高峰秀子は華やかなスター街道を歩みながら とくに、“強き女”として記憶される女優ではなかった。 名だたる監督たちの元で、着実に映画産業を支えてきた一面と、 仕事に対する厳しさ、プロフェショナルを生涯失わなかった女優として その名を残した軌跡は、文字通り大女優とよんで差し支えない。 そんな高峰秀子という女優について、 ここでは、成瀬己喜男作品における高峰秀子をめぐって、 改めて書いてみたい。
 映画・俳優
映画・俳優一時期“ツンデレ”という言葉がもてはやされたが、 ぼくにとっての元祖ツンデレ女優はモニカ・ヴィッティ、その人である。 彼女を思い浮かべるとき、多くの観客はまず、 沈黙の中に立ち尽くす姿を想起するだろうか? 無機質な建築、荒涼とした風景、途切れがちな会話。 その中心で、彼女は何かを語ることも、激しく感情を噴出させることもなく、 ただ世界と噛み合わない感受性として佇んでいる。 それは、ミケランジェロ・アントニオーニ映画におけるヴィッティであり ふたりの巡り合いが生んだ、 20世紀後半の映画史に燦然と刻まれし、最も象徴的な「虚無の女性像」である。
 映画・俳優
映画・俳優伝説と呼ばれしものは、永遠に燃え上がるために、この世を早く去る。 そんな格言めいたことばを、ふと呟きたくなるひとりの女優がいる。 彼女の名前はフランソワーズ・ドルレアック。 いうまでもなく、妹は歳は一つ違い、 フランス映画界の大女優カトリーヌ・ドヌーブ、その姉として名が刻まれている。 世間広しといえ、ぼくにとって、美しい姉妹といえば 映画史のなかで、この二人以上に比較しうる存在がいない。 さらにいえば、ぼくは圧倒的なまでに姉ドルレアック派なのである。
 映画・俳優
映画・俳優アヌーク・エーメは実に恋多き女だった。 4度の結婚、離婚を繰り返している。 そのなかには、『男と女』で共演をきっかけに結ばれた サラヴァを立ち上げたSSWピエール・バルーも含まれる。 蜜月期、わずか3年の月日だが、遊吟詩人的なバルーとの恋もまた 詩的インスピレーションの賜物だったにちがいない。 ピエールはのちに「彼女は嫉妬深いところがあってね」、 そんなことをいっていて、一気に現実に引き戻された記憶があるが、 それでも、スクリーンを通して見る彼女が魅力的だったことに なんら変わりはなく、その女心に寄り添いたくなる男たちにとっては そのギャップこそが彼女へと恋を走らせてしまう要因なのかもしれないと思った。 多分に漏れず、ぼくもまた、そんな女優にときめいた。

クリエーターlopyu66によるアウトプットウェブ
住所
123 Main Street
New York, NY 10001
営業時間
月〜金: 9:00 AM – 5:00 PM
土日: 11:00 AM – 3:00 PM
