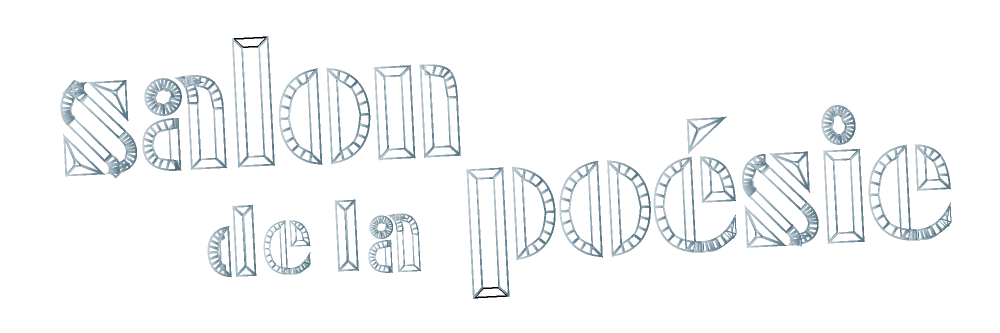詩とは甘やかさのカーブを表すメロディとは別個のものである。
ジャン・ジュネ

詩は万人に よって書かれなければならない、とロートレアモン伯爵はいった。
ポエジーとポエムを混同するなかれ、とコクトーはことあるごとに書いた。
詩は行為である。そう書く瀧口修造は詩を実践した。
詩とは、なんにでもなりうるメデュームのようなものか。
いいかえれば、どんなものにも詩は存在する、とロピュ自身は考える。
タルコフスキーやパラジャーノフが映像で詩を書けば、またゴダールは詩を映像に持ち込み、ミロやクレエが絵の具で詩を描き、マン・レイが光で詩を描いた。タケミツは音符で、寺山は演劇で、大野一雄は肉体で、ジョアン・ジルベルトはギターと囁きで、マイルスはトランペットで……
あまた大勢の表現者たちがそうであったように、ことあるごとにポエジーに跪いた。
エンジンのない自動車、スクリーンのない映画館なんて考えられないのと同じように。
空気がなければ、太陽がなければ生きてはいけないように。
あるときに詩はすらすら流れ出て、表出する字幕だ。
それを写し取る行為、およびそこから抽出した言葉が詩と呼ばれる。
言葉の墨流し。魂の吹き流し。
あるとき、子どもたちの砂遊びであるところの詩。
また、寝言であり、落書きでもある詩。
究極には、詩は、あらゆる存在のざわめきの、具現的な表出なのだ。
しかし、ことばが、ことばとして機能するぎりぎりのところで、
それは、それゆえの血を流す。戦いがある。苦悩がある。
詩を生きることは痛い。
詩人であることは奇跡である。ゆえに美しいのだ。
詩人よ、詩を書くことが重要なのではない。
見者たるランボーは、詩を書くことを放棄するという新たなる詩を選択したわけではなかったか?
とはいえ、ここでは、行為の詩ではなく、言葉としての詩表現を実直にも試みている。
多くの詩人と変わらず、同じことをやっているように見えるかもしれない。
それが詩なのか、はたまた散文なのか、つぶやきなのか、といった厳密な区別は不要。
価値がある、意味がある、そして何よりも高尚だというような思いもまるでない。
詩を書いた、というだけのことである。
詩と戯れ、詩にまみれ、詩と格闘したに過ぎない。
もっとも、書いたのではなく、啓示のようなものを受けて、言葉を素直に書き連ねていったに過ぎない。
その意味では、詩を書く行為は祈りにも似ているし、純然たる神との対話なのかもしれないと思った。
▶︎ポエトリービーイング
・水の気絶
シュルレアリスムによる自動手記のような詩に影響されていた時期に書いた。書いたといってもパソコンとフォントとの関係さえ知らず、何食わぬ顔でコトバを打っていたに過ぎない。ふとしたきっかけから出来上がってしまったオートマティズムな詩篇。意味もなければ、今読み返しても特別の価値も見当たらないが、自分のなかの未開の眼が開かれたコトバであることには変わりはない。
・高貴な唇
行為が詩であると気づいたときに、その一環としてことばが、あたかも詩のような形で編み上げられた詩集。
・孤独詩
つぶやきに人が群れるなら、詩にだって群れていい。だが詩には群れない。詩が群れることを許さない。そんな孤独な言葉を詩と呼んでみる。
▶︎浪花ポエジー
浪速に生まれ育った人間は詩というものに出会って、詩を書くことを覚えたが、実は覚えたのは学問の詩、形式の詩でしかなかった、しょせん、詩とは生身の肉体をもつ生き物なのだ。
▶︎オマージュ
日常の延長下において、出会ったアーティストたちに、こころから敬意を表したい一心で無心からコトバを紡いだロピュからのオマージュ集。