ジュリエッタ・マシーナ小論法
ミューズであることの孤独と永遠 ぼくが愛してやまない映画作家、フェリーニの妻でありミューズであったジュリエッタ・マシーナが、そのフィルモグラフィのなかで彼女が出演している作品はさほど多くはない。おまけに、いつも、どこかバ...
 映画・俳優
映画・俳優ミューズであることの孤独と永遠 ぼくが愛してやまない映画作家、フェリーニの妻でありミューズであったジュリエッタ・マシーナが、そのフィルモグラフィのなかで彼女が出演している作品はさほど多くはない。おまけに、いつも、どこかバ...
 映画・俳優
映画・俳優数あるロマンポルノのなかでも、 ひっそりと置き去りにされながらも、記憶に残る一本の映画がある。 小沼勝監督による『OL官能日記 あァ!私の中で』にふれてみよう。 華のある傑作というより、むしろ埋もれてしまう作品であるにもかかわらず、 そこには70年代という時代の“自由の匂い”が、 いまなお、微かに漂い続けている強烈な一本として忘れ難い映画だ。
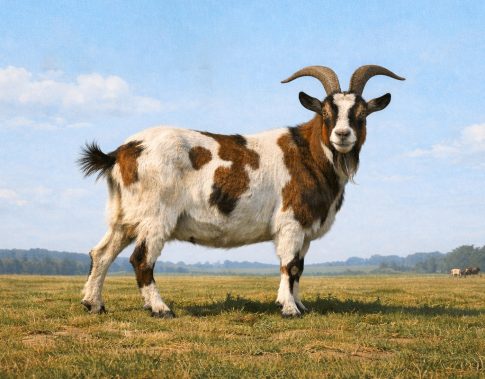 音楽
音楽一度、山羊座生まれのミュージシャンを特集して 「山羊座生まれの同志たちに捧ぐプレイリスト」なるものを作ったのだが、 今日は、その第二弾で、ちょっとこれまでの路線を外した幅広い層から 同じ、山羊座同士の絆をもとに、出世頭のボウイの曲にちなんで 「ALL THE CAPICORN MUSICIANS すべての山羊座野郎のためのプレイリスト」を作ってみよう。
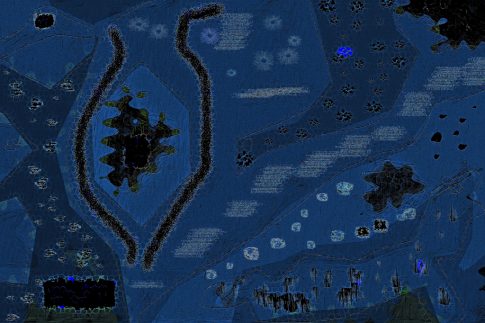 音楽
音楽正月三が日にさっそく雪が降った。 で、ちょっとばかり積もった。 やっぱり、雪があるのとないのとでは冬の空気が全く違うんだよな。 なにしろ景観が変わる。 ぼくは冬生まれだから、雪の冷たさを皮膚感覚で感じるし これがけっこう好きな人間だ。 降り積もった雪の上を初めて踏み締めるときの、 あの感触や音がいまだに好きだ。
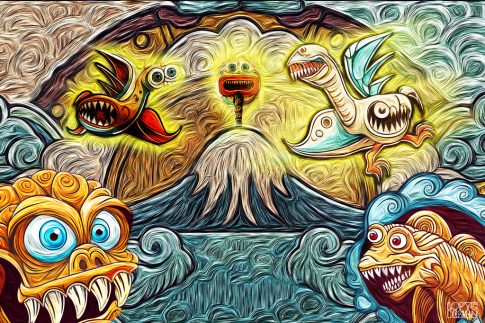 音楽
音楽今年の目標はなんですか? そう聞かれると、いつも、うまくいえなくて困るんだけど ないよりあったほうがいいのかな、やっぱり。 漠然と過ごしているだけじゃつまらないだろうし。 で、目標はなにかというと、夢を追うことなんじゃないかな? 歳を重ねれば、当然、先が見えてくるし、限界もわかっている。 いまさらやっても遅いって思うかもしれない、 でも、誰の夢かといえば、自分の夢であって、 だれからなにかを言われる筋合いはないわけで。。。
 音楽
音楽年があけましたね。 2026年、丙午スタートです。 さて、どんな一年になるんでしょうか? ただ、一年って早い。あという間にすぎてゆく。 でもこうして無事新年を迎えられたことがなによりの喜び。 歳を重ねると、些細なことが幸せに思えてくるもんです。 こうして、好きなことをしながら、のんびりすごせるお正月。
 アート・デザイン・写真
アート・デザイン・写真そんな思いを抱えながら、冬枯れの硯公園を抜けた世田谷美術館で 創設30周年を記念しての開催中の「つぐ minä perhonen」展へと足を運んだ。 ミナペルホネンは、北欧、とりわけフィンランドの空気をまとい ミナとは「私」を、ペルホネンとは「蝶々」を意味する ファッション・テキスタイルブランドである。 ここ、日本を拠点に、ひとつの職人文化を継承する、 そんな生産チームを形成している。 実はこのことが、生み出された生産物共々、興味深く そのブランドの魅力にもなっているのだと思う。
 アート・デザイン・写真
アート・デザイン・写真今日はクリスマス。 ということで、クリスマスにちなんだ映画を取り上げようと思う。 クリスマスのちなんだストーリーは、古今東西、 バラエティに富んではいるのだが、 個人的な一押しでいえば、 少し前のビリー・ワイルダーによる名作コメディ、 ジャック・レモン主演の『アパートの鍵貸します』か ハーヴェイ・カイテル主演、ウェイン・ワンの『スモーク』あたりがズバリなのだが、 ちょっと渋いところで、ジョン・フォード、ジョン・ウェイン主演の 『三人の名付け親』といきたいところだが、 今回取り上げるのはそのクリスマス西部劇から着想を得たという、 今敏による『東京ゴッドファーザーズ』というアニメだ。 この作品は映画という名のアニメであると同時に 単なるアニメ以上に見どころ満載の映画でもある。 実に興味深い現代的な視点がいくつも投与されているが、 シリアスすぎるでもなく、 かといって、コミカルなその場主義的な 単純な物語に収斂しない“心に残る”作品として、語りたい魅力がある。
 アート・デザイン・写真
アート・デザイン・写真北欧のフェルメールなどと、なんとも安易な形容が付いてはいるが その絵を見つめていると、あながち、的外れでもないなと思えてくる。 デンマークの画家ヴィルヘルム・ハマスホイの室内画に惹かれている。 その静謐さ、ミニマリズムはもちろん その内向性ゆえの思いを秘めた気配に、 なにか、そそられるものがあるからだろうか?
 映画・俳優
映画・俳優クシシュトフ・キェシロフスキによる『ふたりのベロニカ』には ポーランドとフランス、この二拠点それぞれに生きる若い女性がいる。 ふたりは面と向かい合うことはないが、見えない糸で繋がっている。 しかも、同じ時刻に生まれ、名前も見た目も瓜二つ。 そんな透明な糸が、互いに知らぬ者同士を天上から操るかのように、 運命の鼓動を、どこかで虫の知らせのように鳴らしはじめる。 そんな偶然を、声ではなく、光でもなく、 まずは音楽によって雄弁に語り始める、異様なまでに繊細な物語にせまってみよう。