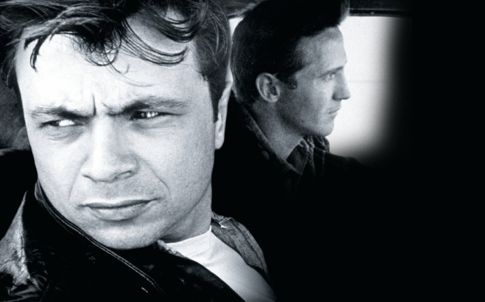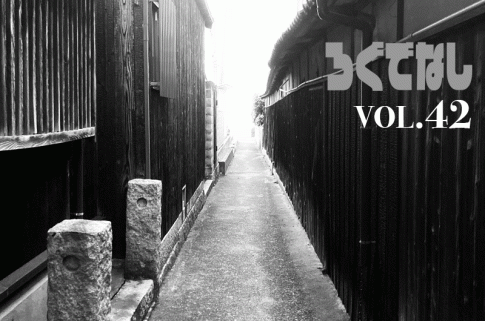リチャード・ブルックス『冷血』を視る
そうした文学的傑作から、リチャード・ブルックスよる映画版をみると 「忠実な映像化」という枠組みからは微妙に逸脱して 新しい倫理観と表現手法に挑戦しているのがわかる。 被写体との距離を取るカメラ、断片的な記憶の再構成、 そして観客を不快にさせることでしか語れない真実が暴き出される。 同時にこの映画は、 文学と映画という表現形式の本質的な違いを浮かび上がらせている。 つまり、事実をどのように"物語る"か、その構造の差異が興味深い。 とはいえ、動機そのものは映画にも読み取れない闇として描かれていた。