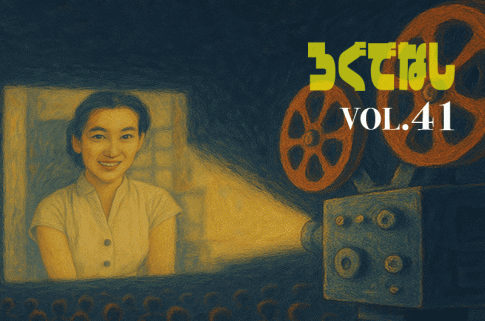入江悠『あんのこと』をめぐって
入江悠の映画『あんのこと』を観たとき、 街を彷徨う一人の女の子の後ろ姿に言い知れぬ孤独を感じた。 シャブ、売春、不登校、彼女の闇はことのほか深い。 ぼくはその“誰か”の視点でこの映画を受け止めたいと思った。 それはヴェンダースの『ベルリン・天使の詩』のような、 誰にも知られず、触れられず、完全な他者として ただ見つめることしかできない天使の視座として、 あんという女の子を見届けようと思った。 でも結局、ぼくらは何もできないということを知るだけである。 この世界では、それは絶望という言葉に置き換えられる