美という奴は恐ろしい怕(おっ)かないもんだよ! つまり、杓子定規に決めることがないから、それで恐ろしいのだ。
ドストエフスキー『カマラーゾフの兄弟』より
アールロピュット目録
▶︎Illust&Drawings
絵と一言で言っても、落書き程度のものからキャンバスに絵の具で描いたタブローのようなものまである。ここでは主に紙に鉛筆一本で、というスタイルで始めたもっともシンプルなイラストを中心に、コンピューターを使って仕上げたものを含む絵を紹介します
- Afternoon Opium・・・A4の白い紙にシャーペンで一筆描きで出来上がったドローイングシリーズ
- Afternoon Opium(DIGEEP)・・・紙にシャーペンで一筆描きのドローイングをデジタル加工したシリーズ
- Illustchop・・・「Illustorator」というデザインソフトで作成したベジエ曲線による図形を、写真用レタッチソフト「PHOTOSHOP」で加工仕上げたシリーズ
- LAND-EX-APE・・・チャネリングのようなメソッドで、形なきもの、抽象的なイメージを捻出するコンセプトで始めたデジタル人類風景画シリーズ
- ROUGH-KITSCH・・・「LAND-EX-APE」にデジタルペンの落書きを加えたデジタルドローイングシリーズ
- キャラアクター・・・ベジエで編まれた造形キャラクラーたちを、空想科学的にキャラクタライズされ個としての命を吹き込んだシリーズ
- シウルレアリスム・・・シュルレアリスティックな塗り絵イラスト
- カオコズミックサロン・・・墨で顔をいただけのシリーズ。
- ワルあ描き・・・色鉛筆で絵のモチーフ、アイデアのメモがわりに始めたシリーズ
▶︎Sclupture
彫刻と言っても粘土細工といってもその辺りの解釈はどうだって構いはしない。手を使って粘土を捏ねて顔らしきものを作った。それは純粋に子供の頃ワクワクして泥だらけになって土に触れた感動を呼び起こし、その延長上に出来上がったシリーズ。
- 仮面彫刻シリーズ「Don’t mask my why」・・・粘土を使った顔の彫刻シリーズ
- 陶芸シリーズ「タナポッタ」・・・土、釜、薬液といった本格的な陶芸プロセスを経た作品集。
▶︎Assemblage
簡単にいえばジャンクアートであり、立体的なコラージュであり、ちょっと難しく言えば精神の浄化作用を喚起するある種のお遊びといったアート作品である。
- 箱庭治療シリーズ・・・主に木箱、時にはキャンバスの裏地を利用し、そこに廃品や日常のガラクタを適度に並べ、彩色したりしながら一つの抽象画にようなイメージを構築したシリーズ。ユング心理学の考え方を取り入れながら発展した「箱庭治療」というコンセプトをそのままアートの作品として取り入れている。
▶︎Photograph
言葉と同様に、写真ほど誰もが身近に感じるメディアもない。これほど浸透した写真において、何らかの付加価値を生み出すとすれば、撮る側に明確な意図があるか否か、ではないだろうか?
▶︎Booklets
本を出したいという知的な欲求を、編集からデザイン、製本に至るまでを単にカラーコピー等を駆使して全て自前で作ってしまった。
- 小冊子シリーズ・・・個展の図録から言葉遊びシリーズ、詩集や画集に至るまで「ロピュール出版」の出版物として限定で作ったシリーズ。
▶︎Exhibition
芸術にあらず、弾けるアウトサイダーは魂の自由を謳歌する
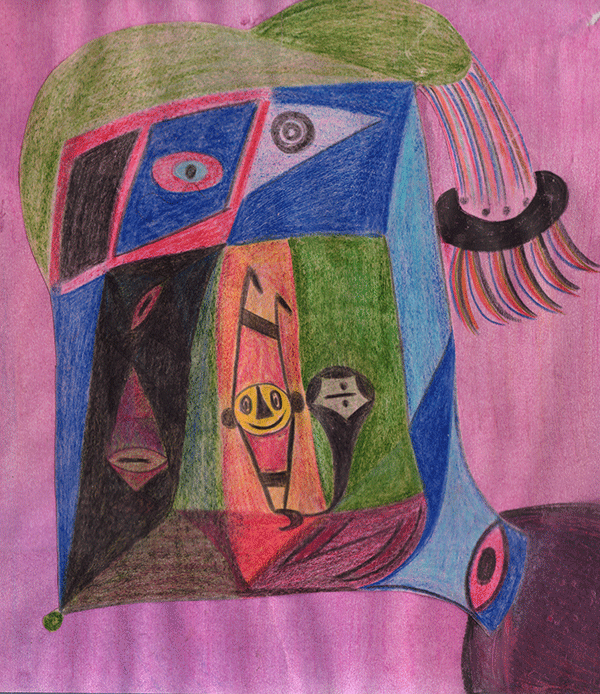
ジャン・デュビュッフェに代表されるアール・ブリュットの作家たちの夢見るような錯乱ぶりや、子供たちが描く無邪気なデタラメ作品を見るときのときめきを、いったいなんと説明すればいいのだろうか? 稚拙だと一言で片付けることほどつまらない返しはない。そもそも一枚の絵を前にした時の価値基準など、描く側にすれば全くどうでも良いことではないか? 果たして人はそれを何と比べようというのか? まさか、絵画史上の名画とでも?
反面、たかが絵へのリアクションを前に、どこまでの意思やどんな思いが込められているのかは定かではないが、出来上がった絵は所詮絵なのであって、当の本人でさえその価値や意味をわかっていないということは十二分にあり得ることだ。作品を作るということは確かにすこぶる楽しいはけ口である。と、同時に、ひどく困難を伴うことでもある。無から有形へと向かうエネルギーの神秘と驚き。意識的であるほどに頭を悩ませる。授かった命を無事出産させようと、十月十日の月日を後生大事に過ごさねばならぬ妊婦の気持ちがいかがなものかは知らないが、どこか似ているのかもしれないと思うことがある。
ある時は、ウミガメの産卵のごとく、自然にポコポコと紙上にひたすら積み上げられてゆくかと思えば、ある時は金縛りにあったかのように、身動きとれぬ痙攣の身にやつし冷や汗をかく。ウンウンうなっても、ウンともスンともいかない窮地で、手の進まぬもどかしさを理解できるだろうか? 要するに、個人的にはその過程にこそ美の真実があり、美学というものがあり、絵の価値基準としては、幾分考慮の余地がありうるのかもしれないと思っている。
時間を要し、苦心したからといって納得のいく物が生まれるとはかぎらない。しばし、ゲイジュツにおいては、身を削る、魂をすり減らすとはよくいったもので、魂にとっても、これほど残酷なことはない。しかし、いざ、作品を創るという行為を客観的にとらえなおしてみるならば、作品とは、あえて創り出すものではなく、結局のところ誰かに、あるいは何ものかによって創らされているのではないのかとさえ思うのである。いわば、創作行為は、選ばれしものだけが携わることのできる特別なゲームなのではあるまいかと。一度懐胎したイメージを無事放出するまでは、時として義務のようにズシリとのしかかってくる、そんなプレッシャーというものもあるのだ。よって、我々クリエーターは、そのことに無自覚ではいられない。アンテナは、たえずそうした波動を察知し敏感に反応するのだ。究極には、意味のないところに意味を生じさせることでもあり、所詮、それは創造主であるところの神の御業であって、我々の感知するところではないとさえ言いたいのだ。
自分では、これまで美術の道を志すべくして志したことなど一度もない。幼児の衝動と何ら変わらない動機を絶えず抱え込んでいるだけである。いわゆる美術教育などとは無縁の人間であり、どちらかといえば、美術音痴の部類であって興味すらあったとはいえない。教養的なバックグラウンドからも縁遠く、実にひどい美意識を植えつけられ育ってきたものだから、手先が器用で、上手く描ける人間が正直うらやましいと思うときもあったが、同時にどこか人ごとのようにも思ってきた。まさか、自分に絵など描けるはずがないとさえ思っていたのだ。ところが、それが、どこでどう転んだのかよくわからないが、いまではそれがもうこの手の内に、皮膚感覚としてしっくり馴染んでいるではないか。文字通り、評価さえ問わねば、いっぱしの画家として胸を張れるまでに、しっかりと画業に根ざして実にもなっている実感があるのである。これをして、世間でいう開眼、あるいは天職とでもいうのだろうか。
もちろん時代の移ろい、コンピューターというテクノロジーの恩恵は無視できない。レオナルド・ダビンチの時代にコンピューターがあれば、などと馬鹿げた想像を膨らませる意味はないが、逆に、時代が入れ替わったとしても、テクノロジーだけに依存しても、真の傑作は生まれ得ないことを知っている。所詮絵や創作に、マニュアルや評価など不要なのだ、そう気づいていたことは幸運だったと思える。だからこそ、ただ無心に絵と向き合えるのである。よって絵が描けないと頭を抱え込むことはないし、世に問うて、あまりの反応のなさに絶望の思いに暗く沈むこともない。アール・ブリュットと呼ばれる作家(本人たちの自覚はともかくとして)の、あの稲妻のようなインスピレーションこそが、我が指針であり、魂への啓示なのだと思っているのだ。
「上手くなくていい」ということは、反対に上手くあることがどういうことかという視点の裏返しである。上手く描けば人に賞賛されたり、それによって優越感を持ってみたり、場合によっては金銭的な価値に繋がる、という意味を含んでいる。それは絵の価値とは全く関係がないのだが、そうしたことに必要以上に関心が行くという視点をもつことはない。全て必然的にこぼれ落ちる選択肢である。オカモトタローがいうところの「なんだこれは!」的なものの希有さを体感し自負している者からすると、何も特別な物言いではないだろう。かつて、“へたウマ”などというジャンルもあったが、作品そのものが、何かに導かれるがごとく、ひとりでに出来上がるということを経験してしまった感動は、神の名を語らずとも、おそらく説明のしようがないほど純粋で、高次元のことに違いないのだ。
ここに作品集と銘打っての、一同に介した表現形態は、ジャンルがどうであれ、同一人物の、同一の発想からうまれ落ちた産物である。個の所業である。瞬間の閃きで処理できるコトバの表現にくらべれば、何倍も時間も労するし、それなりに物理的な場所(スペース)や技術も必要になってくる。そこに見え隠れする重みは、魂のそれと、時間の濃縮の混合物といっていいのだが、創り終えたあとは、なにもなかったかのように、ふわっと中から魂が抜けるようなそんな心地よい脱力感というものに包まれる。それでも他人事のように、電信柱に小水をひっかけて立ち去る犬のごとく、次へ次へとただ向かいたいという衝動だけが襲ってくるのだ。ふと、冷静にまわりを見渡せば、実に膨大な量の作品群に取り囲まれているのに気づく。よくもまあ、こんなものを次々に生み出したものだ、というある種の達観した他人事なのである。その充足や高揚は決して他人には説明はつかないし、理解されえないものだ。
ここまでくると、作品の出来不出来にかかわらず、どれもがわが子のごとく可愛いと思うのは飾らぬ心情である。何かが欠けただけで鬼子母神のごとく、哀しく狂乱する。そんな作り手がたまたま自分であっただけで、もし、かりに、これがまったく見知らぬ赤の他人の作品であったとしても、その作品には目を奪われたにちがいないのだ。その出現に出くわせたおどろきにこそ、十分な共感と愛がうまれる落ちる。この弾ける魂の発露を、ひとまずアール・ロピュットとでもよんでおこう。このロピュ自身を媒体として生まれた生の芸術がここにあるという意味で。


