被う心理境、世にも優雅なティーカップ
かつて・・・それはベルリンの壁崩壊から5年を経た1994年
ドイツの連邦議会議事堂ライヒスタークを、
堂々布で被ってしまったクリストとジャンヌ・クロード夫婦
このアーティストによる行為は、その規模と意義において、
美術史のみならず、劇的な南北統一を遂げたドイツの歴史にも、
大きくその名を刻みつけることになった。
構想から実現まであしかけ24年間を要し、そのプロジェクト総費用10億。
包んだほうも包んだほうだが、許可したほうも許可したほうだ。
もっとも、永年にわたる分裂自体、
あるいは対立の本質を決しておおい隠すことはできない。
それからすると、物理的に表層を被ってしまうという計画は、
いくら規模が破格であれ、かつての「ベルリンの壁」を越えるほどに
困難ではなかったというべきか。
価値のわからぬものにとってみれば、
これほどの「無駄」=ナンセンスな事業はなかろう。
芸術が所詮「無駄」にどれだけ付加価値を派生せしめるか、
ということだとすれば、
なぜ彼等が「被う」という行為に執着し、
議事堂なのか、ということにスポットがあたれば、
その価値も浮き彫りになるのというわけだが・・・。
さて、人というのは、たえず隠蔽された中身を見たいものだ。
そんな心理が働いているかどうかは別として、
さしずめ、日本ならそのようなことは
“問屋が許さない”たわごと扱いを受けるにちがいない。
あれほど隠蔽上手な役人や政治家の、
何でもかんでも包装してしまうことに長けた
国民的土壌という皮肉を背負いながら。
仮に都庁あたりを被ってみるとするとどうなるのだろう?
まあ、ビルによじ登ろうとする「蜘蛛男」が
いとも簡単に捕まってしまうぐらいだから、
結果はおのずと知れている。
そんなだいそれた事業はさておき、
ならば、まず身近にあるものを気紛れに被ってみることにでもしよう。
たとえば、コーヒーカップ&スプーンなどはいかが? しかも毛皮で。
クリストに先駆けること半世紀とすこし、
こちらドイツ人の父とスイス人の母をもつ女性アーティストの、
なんともエロティックで大胆な発想によるものである。
名はメレット、姓はオッペンハイム。
モンパルナスの三大美女と呼ばれたひとりで、
マン・レイなどとの交流でも知られ、
当然のことながら、周りの詩人や画家達のミューズであった。
「もっとも因習にとらわれない女性のひとり」と評したのは
そのマン・レイ自身で、そのモデルとして、
「猥褻さ」をめぐり物議を醸したというヌード写真
「ヴェ-ルをつけたエロティック」(1934)を発表したり、
女体盛りならぬ裸の女性にご馳走を盛った「宴会」(1959)を企画して
シュルレアリストたちを狂喜乱舞させた。
また、親交があり”いっしょに風呂に入った仲”であったという
岡本太郎の回想によれば、
作品に劣らぬほど「お尻に毛がふさふさと生えていた」んだとか。
その彼女とよくルンバを踊り人気ものだったという。
いみじくも、その“ふさふさ”の美女が、
“つるつる”のカップに施した作品(挑発)は、
法王ことアンドレ・ブルトン命名により
「毛皮の昼食」(1936)(原題:dejeuner en ferrures)
と名付けられている。
彼女の一連のシュルレアリスティクな作品たちは、
日用品を使った暗喩として、セクシャリティや性そのものへの開放を目指す
女性の意識を表現しているのだといえる。
たとえば「毛皮の昼食」という作品は、
ティーカップを女性器にみたて、
毛皮はその女性器を覆う陰毛、
スプーンは相対する男性器を暗喩しているというわけである。
その意味では、思わず、“女版デュシャン”などと呼んでしまいたいところだが、
彼女自身は、そうしたセクシャリティによる比較など
まったく意に返さない自由な精神性に基づいているのだから、
さして意味は無いだろう。
これによって、そのシュルレアリスム史に
惨然と名を刻んでいるところだが、
他のコラージュやデッサン、詩などを総合すると、
彼女の神髄は、やはり、政治的な背景などとは無関係に、
その因習になどとらわれることのない、
「永遠のアマチュアリズム」という精神の具現者ということであり、
それゆえ晦渋なシュルレアリスムというイメージからもするりと逃れ、
こんこんと湧き出る泉のような奔放なイマージュの源泉を酌むところ、
つまりはたえずふさふさと生い茂っている
その泉に棲まう真の妖精だったことに、はたと気づかされるのである。
The velvet underground : Venus in furs
メレット・オッペンハイムとその作品「毛皮の昼食」には、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのファーストアルバムに収録のこの「Venus in furs」を捧げましょう。なんとも気だるく呪術的な弦楽器のドローンの白日夢。そんな非日常だからこそ、「毛皮の昼食」はぴったりかもしれません。







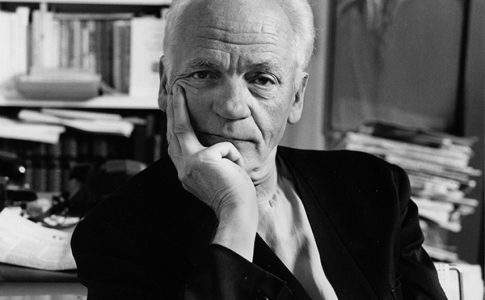





コメントを残す