音見御供感傷記 2019.4.4
2年前、桜の花が咲き誇るもまだ肌寒い四月の東京で、
元ジャパン、ポーキュパイン・ツリーのキーボーディスト、
リチャード・バルビエリの初めての単独ソロライブが
渋谷マウントレーニアホールでひっそりと行われていた。
これはそのときの感想録である。
会場には主にジャパン時代からのコアなファンが
占めていたようだが、
必ずしも盛況であったとは言い難い。
この公演がたった一夜限り、
しかも東京の渋谷という立地条件にも関わらず、
そのホールの半分程度の集客に甘んじてしまう程度の
人気なのが残念な気もしたが、
しかし、会場に足を運んだ人間は
掛け値無しにこの音職人の音を堪能しただろうし、
心からのリチャードファンだったに違いない。
自分としても、無論、ジャパン時代からの
その職人的な音の作り手を注目してきたし、
その音源もリアルタイムで聞いていたリスナーでもある。
とはいえ、その活動があまりに地味すぎて
他のアーティストや音楽、その他諸々のメディアの中に、
どっぷりと埋れてしまうのはしょうがなき宿命で、
この地味なアーティストに目を向ける機会が、
どうも薄くなってしまうのは止むを得ない。
ただ単に元ジャパンのメンバーだったというだけでは
今日までの活動も危ぶまれたに違いなのだが、
幸い、ポキュパイン・ツリーのメンバーとしても
しっかりとキャリアを積んだことで
その活動を継続するに十分なサポートにはなったのだろう。
何しろジャパン時代の功績は
全てリーダーであったデヴィッド・シルヴィアンの元に全て吸収されたというし、
解散後ポキュパイン・ツリーのパーマネントメンバーになるまでは、
それこそ、時にはケイタリングのアルバイトにまで
手を伸ばさずにはいられなかったという噂もあるほど
いわばギリギリのところで、
残るジャパンのメンバーとの活動で生き延びたという、
まさに苦労人なのである。
そんなリチャードを間のあたりにして
基本的には何も変わらないのではあるが、
改めて思うと、その音色の豊かさ、
クラシックからプログレ、
エレクトリックポップからテクノ、アンビエント・トランスにいたる、
鍵盤奏者としての着実な進化をたどることができる
貴重なライブであった。
バックの音はラップトップ中心ではあったが、
例の“ツマミイジリスト”たる動きは健在だった。
ステージの機材およびセットリストを
ここで網羅できないのはもどかしいところだが、
リチャードなりの日本のファン向けサービスとして、
ジャパン時代の楽曲三曲
「Ghosts」「The Foreign Place」「The Experiment of Swimming」を
それぞれアレンジを変え、
またスティーブ・ジャンセンとのアンビエントなアルバム
『Worlds In A Small Room』からの一曲
「Breaking The Silence」を披露してくれたのは感動的だった。
そして、最新のアルバム『 Planets + Persona』や
ポキュパインツリーの楽曲からの音を比較すると、
いかにリチャードの音が進化しているのか見て取れる。
時に重厚でスペーシーなサウンドには
何よりも、一聴するだけで
リチャードらしい音色が選択されているのがよくわかる。
要するにオリジナリティにあふれているのだ。
どこをとってもジャパン時代とさほど変わる気配はないにせよ
すでに還暦を迎え、ますます職人気質の風貌で
単独のライブということで、
ジャパン時代にはまず耳にしたことのない
当人の朴訥ながら誠実なMCを曲ごとに聴けたし、
最後はメインのキーボードをもう使わないからと素早くサインして、
前列のファンに惜しみなくプレゼントしていた、
そんなイギリスの地味で地道なサウンドクリエーター、アルチザンの姿に
もっとスポットライトが当たって欲しい思いと、
これはこれでリチャードらしい活動なのかもしれない、
という両方の思いから会場をあとしたが、
思いの外、その音の残響が心地よく持続する中
肌寒い夜に一人暖かい贈り物を受け取った気分で
どこまでも懐かしい思いにひとりごちるのであった。
リチャードの匠を技を堪能するための10のトラック
A Foreign Place:JAPAN 1979
ちょうど、三枚目『クワイエット・ライフ』に臨むあたりで
それまでの曲調とは一線を画すムードが支配する中で、
こういうエキゾチックなインストを得意にしていたジャパンの小曲のなかにも、
バルビエリの個性が十二分に反映されている。
インストだからこそ、余計にそのあたりが目立つのかもしれない。
THE EXPERIENCE OF SWIMMING 1981
ジャパン時代のインストもののなかでも、屈指の名曲であると思う。
クラシカルな要素とアンビエントが融合した世界は
ある意味、バルビエリの真骨頂でもある。
GHOSTS:JAPAN 1982
ジャパンを代表する一曲でもあるのだが、
改めて聴くと、リチャードがジャパンにもたらした役割が、
けして小さいものではなかったことがわかるナンバーでもある。
幽玄的で、現代音楽的でもあり、
ひとつひとつの音色の抽出が、他のエレクトロニックポップにはみられない
ジャパンというバンドの奥行きの深さを端的に表した名曲だ。
New Moon At Red Deer Wallow:RAIN TREE CROW 1990
シークエンスを繰り返すだけのジャパン時代の曲構造とは真逆の、
即興演奏をメインに据えた新しい方法論で迎えたRTC。
ある種の抽象絵画のような楽曲であるが、個性が実にうまくぶつかり合って
不思議な調和が保たれている。
改めて、高い志向性をもったミュージシャンの集まりだったという思いがこみあげる。
Subtle Body :JANSEN・BARIBIERI・TAKEMURA
竹村延和とジャンセン・バルビエリのコラボは、
竹村のミニマル志向と合致したところで、
リチャードの音色がより前面にフィーチャーされている。
ジャンセン・バルビエリにみられる、
実験的でありながらも、ポップな感性が引き継がれ
三人の個性のバランスがみごとに保たれた名盤だと思う。
Lumen:JANSEN&BARIBIERI
ポストジャパンの活動においては、このJANSEN・BARIBIERIが中心で
常にその良好な関係のなかで活動を続けてきたが、
もともとリズムメイカーだったスティーブ・ジャンセンが
そのなかで、より多面性をもった楽曲志向へと変貌していったように思われる。
Torch Dance:Richard Barbieri & Tim Bowness
ポキュパインツリーのスティーブン・ウィルソンのもうひとつのプロジェクト、
ノーマンのメンバー、ティム・ボウネスとのコラボアルバムからの一曲で
バルビエリの個性が強く出ているナンバー。
ウィルソンもボウネスも、このあたりは
当時からシルヴィアン以外のジャパンのメンバーとの交流が盛んで、
気心の知れた関係のなかで、お互い、その音の親和性にも如実に滲み出している。
Sentimental:Porcupine Tree
ジャパンのメンバーのなかで、解散後
もっとも長く他のバンド活動に従事してきたのがリチャードである。
プログレからの流れを汲むこのポキュパインツリーでは
ある意味、ジャパン以上の成功を勝ち取ったなかで
その個性は最大限に発揮され、リチャードは安定した活動を保証する場だった。
激しさと叙情の入り混じったポキュパインツリーの曲のなかで
このアルバムはリチャードカラーが貢献している一枚でもある。
Medication Time
バルビエリ名義でリリスースされた最初のソロ『THINGS BURIED』からのナンバー。
テクノ、トランス、エレクトロニカとジャンルを自在に横断する音だが、
こちらにほうに、より本質が滲むのは当然であり、
ジャパン時代からの、デジタルというよりはアナログ指向の
バルビエリトーンが随所にフィーチャーされている。
やはり、ポキュパインツリーとソロの音には明確な差がある。
Under A Spell
この二月にリリースされた通算4枚目のソロアルバム。
コロナ事情は、このアーティストにも確実に影を落としてはいるようで、
ほぼ、自宅にこもって作り上げたアルバムだというが、
そのなかで生まれた、新たな波動が支配して、
もはや他の追随を許さない領域で、
これまでにない新たな抽象性と、クールで力強い方向性が示されている。




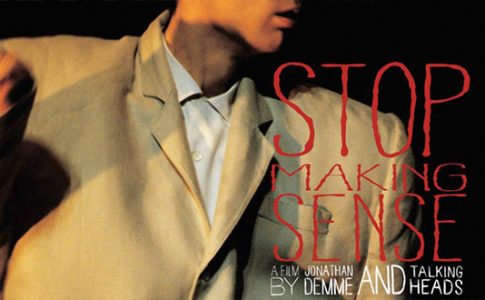

![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-485x300.gif)






コメントを残す